あんず先生のプチ解説コーナー【消費税・インボイス制度】

インボイス制度について少し説明するわね
令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。
インボイス制度とは、8%と10%の消費税率が混在する中でも、事業者が正確に消費税を計算できるように、消費税率や税額などが記載された請求書や領収書等(インボイス)を基に計算する仕組みです。
消費税の計算方法は、「原則」と「簡易課税」の2パターンあります。
【原則】
売上にかかる消費税-仕入にかかる消費税
【簡易課税】
売上にかかる消費税-事業の種類の区分に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額
インボイス制度は、「原則」の“仕入にかかる消費税額”についての制度だから、「簡易課税」についてはまた別の機会で説明しますね。
インボイス制度を理解するには、「原則」の消費税の計算の仕方を理解する必要があるの。
例えば、まりさんがAという商品を仕入れて、販売するという商売をしているとしましょう。
まりさんは、商品Aを11,000円(本体価格10,000円消費税1,000円)で購入しました。そこで商品Aを16,500円(本体価格15,000円消費税1,500円)で売った場合、納める消費税はいくらになりますか?
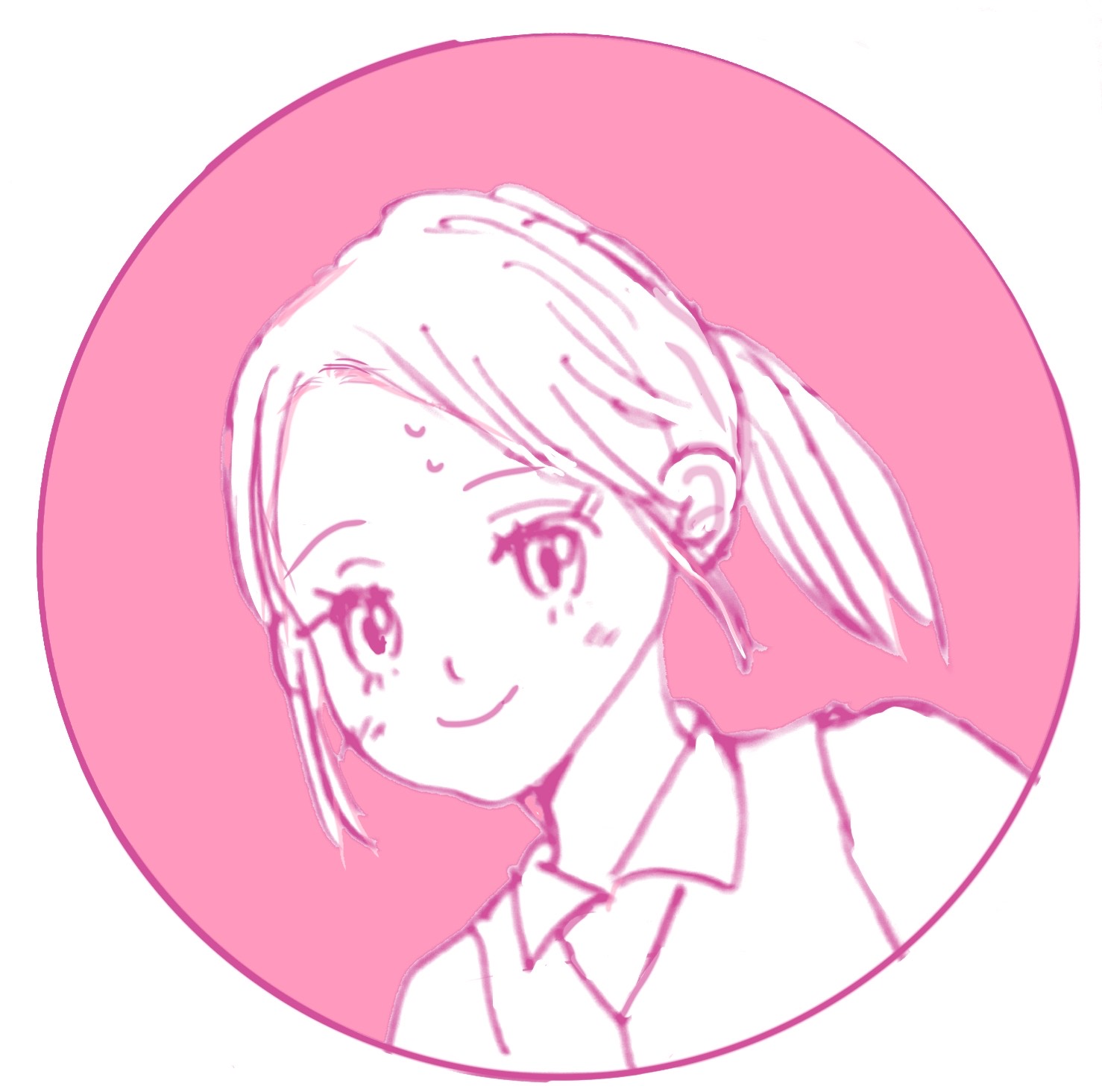
上の原則の算式にあてはめると・・・
売上にかかる消費税1,500円-仕入にかかる消費税1,000円=500円
500円です。
そうだね、これが事業者が払う消費税の原則的な計算になります。

インボイスはどこに関係あるんですか?
インボイスは、仕入にかかる消費税1,000円に関係してきます。
まりさんは当然、1,000円を差し引きたいよね?
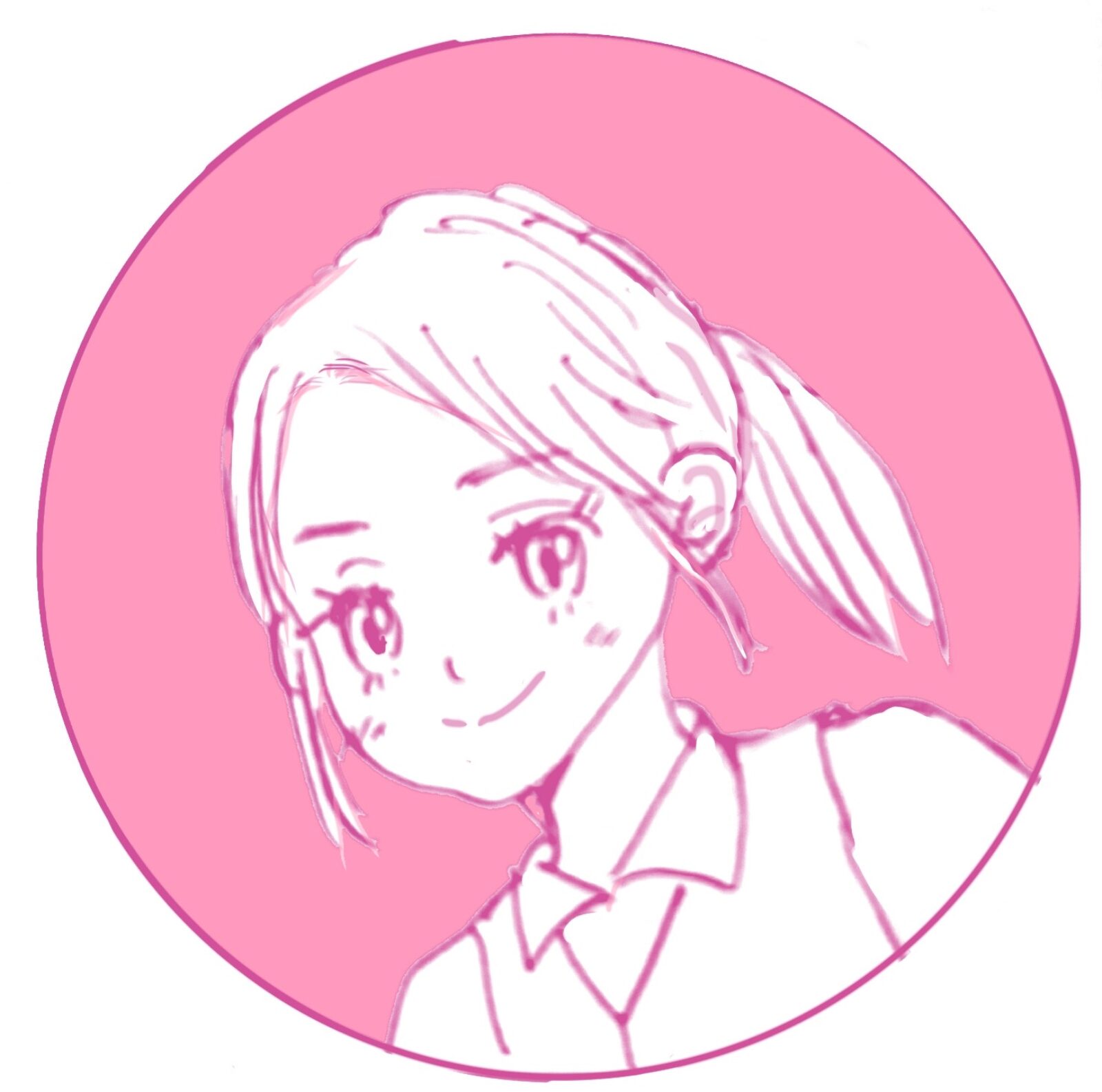
はい、もちろん引きたいです
でも、インボイス制度が始まってからは、国の定めた要件が全て記載されている適格請求書を、まりさんが貰っていない場合は1,000円が引けないことになるの。
この適格請求書のことを、「インボイス」って呼ぶのね。

え~!!
1,000円払っているのに引けないって、損するってことですか?
どうしたらいいんですか?
まりさんは、仕入れ先からインボイスをもらえばいいんだけど、国が定めた要件が全て記載されている必要があるの。

その、要件とは・・・?
①登録番号を含む発行事業者の氏名 ②取引年月日 ③取引内容 ④税率ごとの合計対価額と適用税率 ⑤税率ごとの消費税額 ⑥書類を受け取る事業者の氏名
簡単に言えば、①~⑥の全てが記載されていればいいの。
そこで、新しく出てきたのが①の登録番号なの。
登録番号は、消費税を国に納税していない事業者(免税事業者)は発行してもらえないの。

えっ、消費税を納税しない事業者っているんですか?
全員払うものだと思っていました。
一定の要件を満たした事業者は、合法的に消費税を納税しなくてもいいの。
※ここでは免税事業者の解説は割愛します。
もし、まりさんが免税事業者から商品Aを購入した場合、その事業者には①の登録番号が発行されないので、この時点でインボイスの要件を満たす請求書等ではなくなります。
したがって、1,000円の仕入税額控除は適用できません。
※1,000円全額は差し引けませんが、2029年9月30日までは一部は差し引ける経過措置があります。
今後、まりさんは商品Aを購入する際、どうしますか?

今の仕入れ先では1,000円全額差し引けないので、別の仕入れ先をさがします。
それか、今の仕入れ先に登録番号を取得するようお願いしようかなとも思います。
今の仕入れ先が登録番号を取得するには、消費税を納める業者(課税事業者)になることが必要になるの。
今までは、合法的に消費税を納める必要がなったのに、登録番号を発行してもらうため課税事業者になって消費税を納めることになると、仕入れ先は今まで払わなかった消費税を払うことになるので資金繰りが厳しくなるの。

そっか、免税事業者はインボイス制度が始まると生活が苦しくなる、ってどこかで聞いたことあります。
まりさんから仕入れ先を変更されると、そのお店は売り上げが減少するし、免税事業者にとっては大変な問題なのね。
課税事業者は、もともと消費税を納税しているので登録番号を申請するだけで基本的には今までと同じだから問題はあまりないの。

つまり、こういうことですか・・・?
課税事業者しか登録番号を取得できない。
免税事業者からの仕入れの場合は、①~⑥の要件を満たさないので、1,000円は差し引けない。
でも、2029年9月30日までは一部差し引ける経過措置がある、ということですよね?
そういうことだね✨💯
⭐関連記事